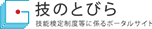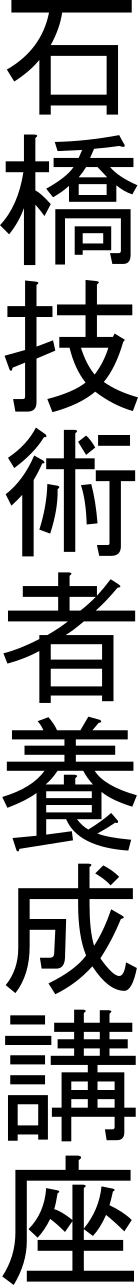PROJECT 14
平成30年度

運営組織:一般社団法人 石橋伝統技術保存協会
拠点:熊本県上益城郡山都町
開始:平成23年7月
Overview
江戸時代から受け継がれてきた
石橋架橋の技術を、次世代につないでゆく。
優れた耐久性で、数百年の寿命を持つと言われる石造アーチ橋(以下「石橋」)。コンクリート橋の普及に伴って多くの石橋が撤去されているなか、その建造技術と文化的価値を後世に残すため、平成23年にスタートした本講座。石橋の保存・修復を行うとともに、座学や実習を通して、架橋技能の継承活動を行っています。平成30年で第8期生を迎え、江戸時代からつづく石工技能の系譜を継承することもできました。その技能は熊本地震で被災した石橋の修復をはじめ、県外各地でも活かされています。
代表者
Interview
代表者プロフィール

代表者プロフィール
一般社団法人 石橋伝統技術保存協会
代表理事
尾上 一哉 さん
昭和28年、熊本県生まれ。石橋の築造・修復をはじめ、土木・建築工事を手がける尾上建設の代表。通潤橋(60ページの写真)の修繕工事をはじめ、全国各地の石橋を守るための調査・研究・工事の活動を行っている。
背景・きっかけ
200年つづいてきた系譜を、
後世に残していきたい。
熊本には江戸時代から石橋に特化した石工集団がおり、師弟関係が脈々と受け継がれてきました。ところが平成10年時点で、後継者は7代目に当たる竹部光春氏たった一人となり、平成23年時点で78歳の高齢。もともと石橋の保存活動は「日本の石橋を守る会」「熊本県技術士会」で行われていました。しかし後継者育成までは手が回らず、伝統技能が途絶える危機感が募りました。そこで竹部氏に指導を依頼し、文化庁をはじめ関係団体の協力を得て、やっと講座が開設できました。
これまでの取組み
受講生を指導者に育て上げ、
継続的に講座を行っている。
「石材加工の実習」「築造・解体・復元・修繕の実習」「既存の石橋群の学習」「座学」を柱にしています。実習は竹部氏、座学は熊本大学をはじめ国内トップクラスの専門家集団という担当分けで、講座をスタート。平成28年の熊本地震は、ひとつの転機となりました。被災した石橋を修復するための専門の技術者が必要となり、竹部氏の弟子として荒木大人氏を、実習講師として5期までの受講生のうち4名を選抜。その後は、10名程度の受講生の受け入れができる体制が整い、継続しています。
今後について
技能者の価値を高め、
全国に石橋を増やしたい。
次に目指しているのは、技能者の価値を高めること。そして、石橋を守るだけでなく、数を増やすことです。平成27年、(一社)石造文化財技術機構が主宰する認定技術者資格制度が開始されました。この資格を、石橋はじめ石造文化財に関する技能の客観的証明として、技能者の地位向上を目指しています。質の高い技能者を輩出することで、石橋の保存、新設への機運を高める。さらには技能者の活躍の機会を増やすことで、彼らの生活保障にもつなげたいと考えています。
PROJECT STORY
「地域の人々の思い出のつまった石橋を、
『日常の風景』として残していきたい。」


荒木 大人さん
指導員
株式会社尾上建設 工事部主任。
熊本県出身。県外で就職したのち、結婚を機に地元に戻る。平成18年、竹部光春氏に弟子入りし、尾上建設に入社。平成28年より石橋技術者養成講座の指導員を務める。
昔気質で寡黙な師匠から
感じた、「技能を残したい」
という想い。

分かりやすく教える難しさ。
再現できない技能の奥深さ。

これからも多くの人に、
石橋の価値を伝えていきたい。

石工たちが腕を発揮する場も増えます。
そのために、これからも技能者を育てていきたいですね。
Column
講座の受講生に聞いてみました。
基礎知識・実地見学・実習のそれぞれが、仕事にも活きている。
石材加工業を営む父の勧めで、和歌山から参加しました。現在は講座を受けながら、石橋の修繕に携わっています。講座では、仕事とはちがった学びがあります。たとえば、築造途中で輪石(アーチ状に並ぶ石)がゆるんだ状態は、現場では見れません。実習では専用の小さな石橋を扱うので、構造を目で確かめられました。また、当社が修繕した庄内の石橋の技術は、実は熊本から伝わったと教わりました。古くから伝わる技能を受け継いでいることは、モチベーションにもなっていますね。

道上 直弘さん